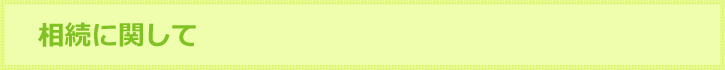

まずは、だれが相続人になるのかを調査しないと始まりません。
被相続人(亡くなった人)が結婚し、子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。
”法定相続人とは”のページで詳しく説明します。
被相続人(亡くなった人)の本籍地の役所にて、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を取り寄せて、相続人がだれになるのかを調べます。
通常、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て調査します。
結婚や引っ越しで、本籍地が移動している(転籍)している場合、昔の本籍地のあった役所で調査しなければなりません。
思わぬケースとして、前妻との間に子どもがいたが、それを家族が知らなかった場合もあり、相続人の調査で、それが判明する場合もあります。
また、養子縁組で幼い頃に引き取られた兄弟姉妹も相続人となるケース、相続人が外国人と結婚して海外に居るケースなど様々です。
一番はじめにしなくてはいけないのがこの相続人調査で、戸籍謄本の収集と相続関係図の作成に取り組む必要があります。
被相続人(亡くなった方)の不動産(土地・建物)、預貯金の調査(各金融機関の残高証明取得)、株式などの有価証券もその評価額を調査します。美術品、骨董品も遺産となります。借金も負の遺産として相続財産になります。
また、被相続人(亡くなった方)が遺言を残されているケースも考えられます。相続財産を調査していると、自筆証書遺言が見つかった、以前公正証書遺言を作成したと聞いた、そういう場面も考えられます。
公正証書であれば、公証役場に行って作成していないか調べてもらうこともできます。
また、相続財産の調査のなかで相続税がかかりそうな場合には、当事務所より相続税に強い税理士をご紹介することもできます。
不動産の調査
市役所の固定資産税課にて、名寄せ帳の写しの取得をして調査を行います。
他にも、権利書、固定資産の納税通知なども資料となります。
預貯金の調査
通帳や銀行からの葉書などを頼りに調べます。
地元の金融機関(唐津市であれば、佐賀銀行、唐津信用金庫、ゆうちょ銀行、JA(農協)に口座を持っている方が多い)に調査を依頼する場合もあります。
有価証券
主に証券会社から郵送されてくる書類、通帳を頼りに調べます。
借金(負債)の調査
ブラックリスト(信用調査機関)へ照会を行います。また、通帳の履歴からカード会社や銀行、個人からの借入が無いか調べます。
生命保険
生命保険は、受取人固有の財産であり、相続財産からは外れますが、相続税の対象になります。また、受取人が被相続人(亡くなった方)になっている場合もあり、しっかりと内容を把握することが大事です。
相続方法の決定とは、原則として相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に、財産を相続するか、もしくは放棄するか、一部だけ相続(限定承認)するかを決めることをいいます。
相続を何時までに行わないと行けないということは有りませんが、相続放棄手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きをしなければなりません。
また、相続人間で法定相続分に基づいて相続するのか、長男が全て相続するのか、土地は長男、預金は次男に相続する等の方法によるのか決定します。
これを遺産分割といいます。通常は遺産分割協議書を作成しますが、預金の場合各金融機関や有価証券の場合は証券会社の書式があるので、取り寄せます。
相続人全員の協力がなければ、遺産分割はまとまりません。
遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や裁判を起さざるを得ない場合もあります。
相続人のなかで、行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人を選任しその財産管理人と遺産分割をするケースもあります。
また、相続人が、認知症の場合、成年後見人を選任しなければならないケースもあります。
遺産分割は、全員が納得しないとできないため、上記のようなケースが事前に想定される場合には遺言書の作成をオススメします。
遺産分割協議書がまとまったならば、財産の名義変更を行います。
不動産の場合は、登記申請を行い、名義を変更します。司法書士にご依頼ください。不動産の名義変更と相続税はあまり関係がありません。相続による名義変更には不動産取得税がかかりません。
預金の場合各金融会社や有価証券の場合は証券会社の書式に署名押印すべき場合があります。
基本的には、押印は実印を押印します。印鑑証明書や戸籍謄本などの書類も一緒に提出すべき場合が多いです。
預金の場合、預金口座の名義変更が完了すると、預金を受け取ることができます。